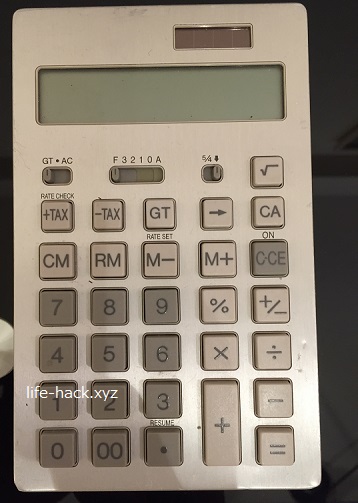忘年会の季節ですね。
1回目の司会進行から、はや5年なぜか司会進行役になってしまいました管理人です。
司会進行って緊張しますよね。
今年社会人1、2年目が司会をする会社も多いのでは?
司会進行は社会人の登竜門。
同僚や上司など大勢の見ている前で司会をするとき緊張してしまいます。
あたふたしているのでは、何とも頼りない印象になってしまいますよね。
出来る限りスムーズかつスマートにやってしまいたい。
ついでに、女性陣の目も気になりますしね(笑)
出来る事なら「カッコイイ!」と思ってもらいたいもの。
もしもですよ…
「えーと」「次は、あ、・・・(頭まっしろ)」となってしまったら
何だこいつ司会もできないのかよ
と思われたら、格好良さをアピールするどころか、
気まずい雰囲気が流れてしまいます。
そんな状況を避けるために司会の台本があれば本番もあたふたせずに進行できますね。
管理人は緊張しやすいので、ある程度台本を作るようにしていましたが、それでもよく噛んでいました。
噛んでいることが先輩にいじられてその時はよかったのですがw
2回目からはしっかり練習と台本を準備していったので、そのあとの司会は安定していきました。
話すことがしっかり入っていれば、安心して進行することができます。
台本を使ってスムーズに進めましょう。
忘年会での司会進行
始めての司会進行。みんなの前で話をするので注目を浴びます。
私も、始めての時は知らない他部署の上司まで来てて「はぁー」とため息が出るほど。
仕事するときより緊張していましたw
安心してください。
実際は自分が思っているほどみんな司会に注目してません。
先輩もやさしく見守ってくれているはずです。
司会進行で、大きなカテゴリーを分けると
- 開会宣言
- 挨拶、乾杯
- 歓談
- 最後(2次会の誘導)
4つに分類できます。それぞれについて見ていきましょう。
開会宣言
開始の告知を行いましょう。
会場がざわついていたら「これから始める」というのを注目してもらうためです。
集合時間が7時でも、仕事で遅れたり早く到着したりするもの。
遅れている場合や集まりが早い場合は「予定通りにするのか」「早く始めてしまうのか」上司に相談しましょう。
挨拶・乾杯
開会宣言が終われば、挨拶ですね。みなさんの飲み物が運ばれたどうかを確認して挨拶に移りましょう

・「〇△課長に乾杯の音頭をお願いしたいとおもいます。」
挨拶と乾杯の音頭は別々な場合と同じ人の場合があります。
締めの言葉を1番上の方にお願いするので、ここでは2番目か3番くらいの立場の人にとりおこなってもらうのが望ましいでしょう。
会社によっては乾杯を1番目の役職に行ってもらうことがあるので、先輩や上司に確認するようにしましょう。
歓談
挨拶が終われば食事に入ります。

時間に合わせて30分ほど食事・歓談の時間をとりましょう。
余興や新入職の挨拶がある場合は
余興が終われば、
ここまでくればあとはもう少しですよ。
最後の挨拶(2次会の誘導)
ここまでくれば大詰め。
挨拶が終わればお開きとなります。
今日は楽しい時間を一緒に過ごすことができ、ありがとうございます。場所の関係もありますのでこれで〇□営業所の忘年会をお開きにしたいと思います。」
二次会に誘導する場合は
これで忘年会は終了です。
会社によって挨拶の順番などは違いますが、大体はこのように流れていくのが一般的です。
ぶっつけ本番の前に、上司や先輩に流れを一度確認してもらいましょう。
できる司会はここが違う
司会進行は緊張するものですが、どうやって進行するのか台本やタイムスケジュールがあれば楽に進行できます。
ここで大事なのが、乾杯や終わりの挨拶を事前に上司にお願いしておくこと。
上司も当日挨拶を求められると困惑したりするもの。
なので事前に直接、もしくはメールで確認しましょう。
あとは、よく私もよく使ってしまうのが言葉の頭に「えー」「それから」
などの言葉。
どうしても文章の間考えたりするときに無意識に使ってしまいますよね。
前回も主任の挨拶で、
えー今季の業績も良く、
えーこの日を迎えることができました。
えー来年も、
えーこの調子で、みんなとともに業績を上げればと思います。
と「えー」の回数が気になりすぎて言葉が入ってこないこともありましたw
間を持たすために行ってしまうのであれば、言わない方が良い印象です。
話すときは気をつけていきましょう。
4つのカテゴリーから司会進行をする方法をお伝えしました。
- 開会宣言
- 挨拶、乾杯
- 歓談
- 最後の挨拶
という感じに進行していけばよいでしょう。
忘年会のシーズン。1、2年目に司会進行は登竜門です。
初めてなので緊張するのはみんなが通る道。
しっかり準備して、格好良さをアピールして楽しい忘年会にしましょう。