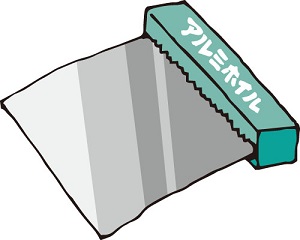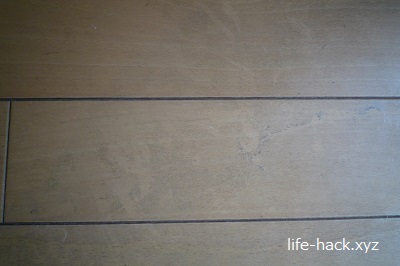趣味の園芸で、みんなを一度は悩ませるアブラムシ!
スギなどの一部の種類を除き、ほとんどの植物に寄生します。
せっかく大切に育ててきた花や野菜に、ぶわーっと大量発生。
ベタベタ、もぞもぞ、気持ち悪い!
その上、アリまで寄ってくるし……。
アブラムシの被害は植物の汁を吸うだけではありません。
モザイク病やイシュク病などのウイルスを土壌に残します。
かかってしまうと、収穫をあきらめることにも。
そんな残念な結果を避けるために、アブラムシを甘く見てはいけません。
見つけたら早めの対処が肝心ですよ。
- アブラムシをみつけたら、どうすればいい?
- アブラムシの発生する期間は?
- どうしてアリが群がっているの?
- アブラムシがつく前に予防したい!
植物と園芸家のにっくき敵。
アブラムシ対策について解説しますね。
アブラムシの駆除5つの方法で撃退!
アブラムシ退治はこの5つが効果的です。
- 筆でコチョコチョ。
- ビニール袋で一網打尽。
- 牛乳スプレー。
- 粘着くん。
- 最後の手段は、やっぱり農薬。
絵筆や書道の筆で、コチョコチョとアブラムシをくすぐるだけで駆除できます。
小さめの植物であれば、ビニール袋をかぶせて鉢底で口を閉じ、数時間放置。
それだけでビニール袋の内側に、アブラムシがぎっしりついています。
これを2~3日繰り返すだけで、ほぼすべてのアブラムシは駆除されます。
しかし、湿気に弱い植物には注意して行ってくださいね。
袋の内側は蒸れて水滴だらけになりますよ。
植物にとっても呼吸が苦しくなってしまうので、様子を見ながら行いましょう。
牛乳と水を1:1で、百均のスプレーボトルに入れ、吹きかけるのも有効です。
手軽で安全性が高い方法なので、アマチュア園芸家のアブラムシ駆除では人気の方法。
牛乳が蒸発して乾燥すると、脂肪分でアブラムシが呼吸できなくなり窒息します。
朝、牛乳をスプレーしたら、夕方に水で植物全体を洗い流してください。
牛乳がついたままになっていると、植物自体にカビが生えたり、枯れる原因になります。
牛乳と同じように、でんぷんなどの成分も、効果が高いです。
「農薬にはどうしても抵抗がある」
という人には、住友化学の『粘着くん液剤 1L』がおすすめ。
1Lで1000円前後で販売されています。
でんぷんをメインとした成分で、毒性が低く、収穫前日まで使用できます。
アブラムシだけでなく、ハダニやタバココナジラミなどの他の害虫にも効果あり。
そのうえ、アブラムシの天敵テントウムシには無害という優れもの。
しかし大量発生して、次から次へと沸いてくるような場合は最後の手段。
農薬に頼るしかありません。
「食べるために育ててる野菜に農薬はちょっと……」
「人体に影響はないの?」
など、心配される人も多いでしょう。
しかし、正しい容量と方法を守れば、人体への影響はほとんどありません。
無理をして無農薬にこだわると、野菜が病気になって収穫をあきらめてしまう結果にも繋がりますよ。
収穫物に影響の少ない初期段階で、適切に農薬を使うことも上手な園芸の基本です。
アブラムシの出る時期は?
- 春から夏にかけて爆発的に増える。
- 秋から冬にオスが発生し、卵を産んで越冬する。
あまり知られていない衝撃の事実!
なんと春に卵から生まれるアブラムシは全員がメス。
しかも胎内で自分と全く同じ、クローンのようなものを増やしていくんですよ。
生まれてきたクローンも、すでに胎内に子供を宿している状態で生まれてきます。
自分のコピーをどんどん生み出して、爆発的に増えていくアブラムシ。
想像するだけで気持ちが悪いですね。
作物に害を与える大量のアブラムシは、このメスだけで構成されたコロニーですね。
ごく限られた期間だけ小さな翅でふわりふわりと飛んで移動します。
それ以外は、ここと決めた宿主植物の上でじっとしたまま一生を過ごしますよ。
秋になると、メスだけのコロニーに変化が現れます。
メスの集団から、急にオスが生まれますよ。
オスを交えた繁殖の場合は、卵で寒い冬を越し、暖かくなって来たら卵からかえります。
卵を産んだアブラムシは、冬の寒さで死滅することが多いですね。
しかし、暖冬の年や、温暖な地域では生き延びますよ。
そのため、西日本の暖かい地方では、季節に関係なく一年中発生する害虫です。
生活環境や条件の良い時に、クローンを使って大量に増殖。
そして気候など条件が悪化すると、子孫を残して休眠。
このような独特の発生の仕方は、ミジンコやカイガラムシにもあります。
人間からは想像もつかない、不思議な生態をしていますね。
意外な事実アリにも注意

アブラムシのいるところに、必ずアリがやって来る。
というほど、アブラムシとアリには密接な関係があります。
アブラムシのお尻からは「甘露(かんろ)」という蜜が出てきます。
アブラムシにとっては排泄物なのですが、アリにとっては大好物。
アブラムシの体は柔らかく、他のいろいろな虫や動物の餌になります。
特にテントウムシはアブラムシにとって天敵ですね。
テントウムシはの食べ物は、アブラムシです。
おいしい甘露を出すアブラムシが、食べられて死んでしまうことはアリにとって困ること。
アリは、テントウムシにかみついて追い払ってしまいます。
硬い体を持つテントウムシも、アリの集団攻撃にはかなわず逃げ出すことに。
アブラムシはアリに、天敵から身を守ってもらいます。
アリは、アブラムシから出る甘い排泄物を餌にして生きています。
アブラムシが住んでいた植物が病気になって枯れてしまうと、アリが新しい健康な植物のところまで運んでいきます。
こういう生態を自然界では共生と言いますね。
アリを退治すると、アブラムシも生きていけません。
そのため、アブラムシと同時にアリ対策もしなくてはいけません。
小さい蟻の駆除方法は?ノイローゼになる前にやること
アブラムシを寄せ付けない方法は
- コンパニオンプランツを植える。
- アブラムシは光の反射に弱い。
- すだれなどの利用。
- 窒素系の肥料を与えすぎない。
- テントウムシを上手に利用する。
同時に植えると防虫や病気対策に効果があるものを、『コンパニオンプランツ』と言います。
唐辛子、ニンニク、ニラ、ショウガ、ナスタチュームなどを、一緒に植えるとアブラムシが嫌がりますよ。
唐辛子を度数の高い焼酎に漬け込んで、水で薄めたものをスプレーボトルで散布するのも効果的。
殺虫効果はありませんが、予防にはなります。
木酢液を500倍に薄めて散布する方法もよく聞きますが、あまり効果はありません。
しかし、即効性はないものの、地道に続ければアブラムシの数が減るのは確かですね。
強い臭いがあり、野良犬や野良猫の糞尿被害も、同時に防げますよ。
アブラムシは光の反射が大嫌い。
園芸用に販売されているシルバーシートで、植物の周りを覆う方法があります。
しかし家庭で簡単に対策するなら、キッチンのアルミホイルや、百均のガスレンジカバーも代用できますよ。
他にも、いらなくなったCDなどを吊るすと、予防になりますよ。
場合によっては、太陽の向きなどで効果がうまく出ないこともあります。
また熱や光を収束して火事の原因になる場合もあるので、燃えやすいものを近くに置かないで下さいね。
6月頃、翅をもって飛んでくるアブラムシには、すだれが有効。
植物の周りを高さのあるすだれで覆っておくと、ぶつかった瞬間に毒を吐きます。
この時、毒を吐ききってしまえば、植物に感染するウイルスがなくなります。
ウイルスを持っていないアブラムシは、病気で枯れる心配は減ります。
窒素系の肥料を多く使うと、アブラムシが好んで寄ってきます。
野菜を大きく育てるためには、適度に肥料を使うことも大切ですが、使い過ぎには注意。
テントウムシなどの天敵を利用するのも良い方法ですね。
ヒラタアブの幼虫、テントウムシは幼虫・成虫ともにアブラムシをたくさん食べます。
天敵の虫がたくさんいるときは、農薬を使うとかえって天敵が死に、害虫が増えることも。
このテントウムシを、人工的に改良したものがあります。
その名も『生物農薬』。
化学物質の力を使わず、自然の食物連鎖を利用して、害虫を駆除する方法です。
テントウムシはアブラムシをたくさん食べてくれますが、飛んでどこかへ行ってしまいます。
なので『飛ばないテントウムシ』として品種改良されました。
商品名『テントップ』として、50匹で5290円で販売されていますよ。
まだ一般の家庭菜園で使用するには高値ですが、将来的には価格も下がるかもしれませんね。
園芸の敵、憎きアブラムシ。
なんとか駆除して、大事な花や野菜を守りたいですね。
アブラムシ対策は、プロの農家でもなかなか苦労するもの。
人と害虫の戦いの歴史は一進一退ともいわれています。
あきらめずに地道な挑戦あるのみですね。
しかし害虫とはいえ、調べてみるとたいへん興味深い生き物だと気付きますよ。
社会性の高さや独特の生態に、生命の進化の神秘を感じます。
もし夏休みの自由研究で作っていた植物が、アブラムシにやられてしまったら、彼らを調べてみるのも良いかも。